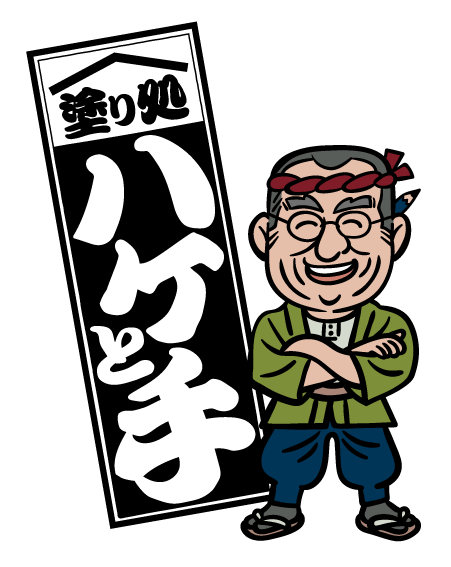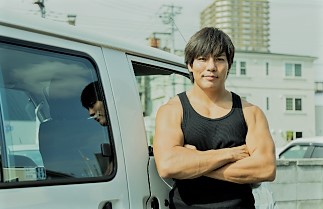2025.10.18
外壁の種類と特徴を徹底比較!プロが教える最適な選び方
外壁は家の「見た目」を左右するだけでなく、家を守る“鎧”のような存在です。
しかし、「どの外壁が自分の家に合うのか分からない」「費用や耐久性の違いが曖昧」という方も多いはず。
この記事では、「外壁 種類」をテーマに、住宅タイプや地域環境に合わせた最適な外壁選びの考え方を、専門施工店「塗り処ハケと手」が現場目線で徹底解説します。
単なる素材紹介ではなく、“30年先も後悔しない外壁選び”を実現するための基準や費用感、メンテナンス戦略まで、すべてをわかりやすく整理しました。
📘この記事で分かること:
-
外壁の種類と、それぞれの特徴・耐久性・コストが分かる
-
環境・立地別に最適な外壁を選ぶ基準が分かる
-
外壁ごとのメンテナンス周期と劣化サインが分かる
-
塗料の種類別に、30年スパンでの費用比較が分かる
-
塗装・張替え・重ね張りの判断基準が分かる
-
信頼できる塗装会社を選ぶチェックポイントが分かる
-
長期的に「コストを資産に変える外壁選び」の考え方が分かる
ハケと手は、日本建設技師協会3冠を獲得しています。

簡単30秒でお見積♪
目次
結論:まず知るべき外壁の“最適な種類”と選び方の基本軸

外壁には数多くの種類がありますが、「見た目」よりも「住まいの条件に合うかどうか」で選ぶことが何より大切です。
たとえば、海沿いでは塩害に強い金属系、寒冷地では断熱性に優れたALCなど、環境によって最適解は異なります。さらに、初期費用よりも“維持コスト”を意識することで、将来の塗装費や補修費を抑えられます。
この項目では、「用途・地域性・維持コスト」という3つの軸から、あなたの家に最も合う外壁の種類を具体的に解説します。
1.1 外壁材の種類は「用途/地域性/維持コスト」で選ぶ

外壁を選ぶ際、多くの方が「デザイン」や「価格」だけに注目しがちです。しかし、外壁は“家を守る装甲”であり、住環境との相性が最も重要です。
まずは以下の3つの観点を押さえておきましょう。
| 選定軸 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 用途 | 新築・リフォーム・重ね張りなど、施工方法によって最適材が変わる | 既存外壁の状態を診断してから決める |
| 地域性 | 雨・雪・塩害・日照など、気候条件に合う素材を選ぶ | 例:海沿い→金属系、寒冷地→ALC |
| 維持コスト | 初期費用+メンテナンス費の合計で判断 | 10年単位での塗装・コーキング更新を想定 |
たとえば、モルタルは自由なデザイン性が魅力ですが、ひび割れ対策が必須です。
一方で窯業系サイディングはコスパが高く、初めて外壁を選ぶ方にも人気。しかし10年程度でシーリング補修が必要です。
また、金属系(ガルバリウム鋼板)は軽くて耐震性に優れるため、重ね張りリフォームにも最適。
こうした特徴を把握しておくことで、“見た目重視の後悔リフォーム”を防ぐことができます。
外壁材は“単体で選ぶ”のではなく、「今の家・地域・維持計画」に合わせて選ぶ。
この考え方こそが、長く快適に住むための最初の一歩です。
1.2 よく使われる主要外壁材7種と、それらを選ぶ基準
現在、日本で主に使われている外壁材は以下の7種類です。
それぞれの特徴と、選ぶ際に注目すべき基準をまとめました。
| 外壁材の種類 | 主な特徴 | 耐久年数目安 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 窯業系サイディング | コスパ・デザイン性が高い。国内シェア約70%。 | 約25〜30年 | 標準的な住宅全般 |
| 金属系サイディング | 軽量・耐震性・塩害耐性。断熱材付きタイプも。 | 約25〜35年 | 海沿い・寒冷地 |
| 樹脂系サイディング | 退色に強くメンテナンスが少ない。 | 約30年 | メンテを減らしたい方向け |
| 木質系サイディング | 天然素材の風合いが魅力。 | 約10〜15年 | デザイン重視の家 |
| モルタル(塗り壁) | 職人仕上げで個性が出せる。 | 約20年 | 和風・洋風問わず自由設計住宅 |
| タイル外壁 | 超高耐久。メンテナンスは目地中心。 | 約40〜50年 | 長期的な資産価値を重視 |
| ALC(軽量気泡コンクリート) | 断熱・遮音・防火に優れた高性能素材。 | 約40年以上 | 寒冷地・大型住宅向け |
選ぶ基準は、「性能×維持費×デザイン」の三要素をどうバランスさせるかです。
特に見落とされがちなのが、将来のメンテナンスコスト。
たとえば「初期費用が高い=損」ではなく、「メンテが少ない=結果的に得」なケースも多いのです。
実際、タイルやALCは再塗装がほぼ不要で、長期的にはランニングコストが低く抑えられます。
逆に安価な外壁材は10年ごとに塗り替えが必要なため、30年スパンでは差が数十万円〜100万円以上になることもあります。
つまり、外壁選びの正解は“今の予算”ではなく“30年後の満足度”。
その視点で選ぶことで、外壁は「コスト」ではなく「資産」に変わります。
簡単30秒でお見積♪
外壁材7種の“特徴・メリット・デメリット”徹底比較

外壁選びで失敗を防ぐ一番のコツは、「素材ごとの特徴と弱点を正しく理解する」ことです。どの外壁にも“万能”は存在しません。
たとえば、窯業系はコスパ重視、金属系は軽さと耐久性、モルタルは自由なデザイン性が強みですが、いずれもメンテナンス方法が異なります。
ここでは、私たち「塗り処ハケと手」が現場で実際に扱う7種類の外壁材について、実際の施工現場で見える本当のメリット・デメリットを専門家の視点から解説します。
1 窯業系サイディング

日本の戸建住宅で最も多く使われているのが窯業系サイディングです。セメントと繊維質を混ぜて形成した板材で、全国の新築住宅の約7割がこのタイプを採用しています。
最大の魅力は「デザインとコストのバランス」。木目調・石目調などの柄が豊富で、比較的安価に外観をグレードアップできます。
しかし現場目線で見ると、弱点はシーリング(継ぎ目)と吸水性。10年ほど経つとコーキングがひび割れ、そこから雨水が侵入して下地を傷めるケースが多く見られます。対策としては、早めのシーリング打ち替えと再塗装をセットで行うこと。特に南面や日当たりの強い箇所では劣化が早いので注意が必要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| デザインが豊富で施工が早い | シーリングの劣化が早い |
| コスパが良くリフォームにも対応 | 吸水による反り・浮きが起きやすい |
総評:コスト重視型には最適。ただし、10年ごとの塗装で美観と防水性を守ることが長持ちの鍵です。
2 金属系サイディング(ガルバリウム、鋼板など)

金属系サイディングは、軽量で強度が高く、耐震性にも優れた外壁材です。特にガルバリウム鋼板はアルミ・亜鉛・シリコンでメッキされた鉄板で、錆びにくく、塩害にも強い素材として注目されています。
ただし、断熱性や防音性は単体ではやや弱いため、裏に断熱材を一体化した「断熱サンドパネル型」を選ぶのがポイント。また、金属特有の“熱伸縮”による波打ち(熱膨張)も見られるため、施工精度が品質を左右します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 軽くて地震に強い | 熱や音が伝わりやすい |
| 錆びにくく塩害地域に強い | 安価な製品は塗膜が薄く色あせやすい |
総評:軽量・高耐久でリフォーム向き。断熱付きタイプ+信頼できる施工店の組み合わせが理想です。
3 樹脂系サイディング

樹脂系サイディングは、北米では主流ですが、日本ではまだ珍しい素材です。塩化ビニル樹脂を使用し、色あせしにくくメンテナンスがほぼ不要というのが最大の特徴。雨や紫外線に強く、再塗装の手間がほとんどかかりません。
ただし、施工できる職人が少なく、材料費もやや高め。また、表面が柔らかいため、衝撃に弱くへこみやすい点にも注意が必要です。
夏場には熱を吸収しやすいため、外断熱性の高い住宅との相性が良いといえます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 塗装不要で色あせに強い | 施工業者が少ない |
| 軽量で地震にも有利 | 衝撃に弱くへこみやすい |
総評:メンテナンス重視派に最適。初期コストはやや高いが、20年スパンで考えるとコスパは非常に高い素材です。
4 木質系サイディング

木質系サイディングは、自然素材の温かみが魅力です。天然木や集成材を加工しており、木のぬくもり・経年変化を楽しみたい方に人気があります。
ただし、木は水分を吸収しやすく、紫外線にも弱いため、定期的な塗装・防腐処理が欠かせません。特に日差しや雨にさらされる部分では、2〜3年に一度の塗装メンテが理想です。
また、防火地域では使えない場合もあるため、建築地域の制限を確認する必要があります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 天然木の質感・デザイン性 | 腐食・変色・反りが起きやすい |
| リフォームや部分交換が容易 | メンテナンス頻度が高い |
総評:デザイン性では随一。自然素材の良さを楽しみつつ、塗り替え前提で長く使うスタイルが最も満足度が高い外壁材です。
5 モルタル(左官仕上げ含む)

モルタル外壁は、セメントと砂を練り合わせて塗り重ねる昔ながらの工法です。職人の手作業によって仕上げるため、唯一無二の質感や表情を持たせられるのが最大の魅力です。
一方で、ひび割れ(クラック)や防水性の弱さが課題です。気温差や地震で壁が動くと、ヘアークラック(細かいヒビ)が入り、そこから雨水が侵入することもあります。
そのため、高耐候塗料や弾性塗料で表面を保護するのが必須です。特に下地処理を丁寧に行うことで、ひび割れリスクを大きく減らせます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 高級感・デザイン性が高い | クラックが入りやすい |
| 形状自由で和洋どちらにも合う | 防水対策が必要 |
総評:職人の技が活きる外壁。ひび対策と防水塗装を組み合わせれば、デザインも耐久性も両立できます。
6 タイル(磁器・窯業タイル)

タイル外壁は、耐久性・高級感ともにトップクラス。雨風・紫外線にも強く、塗り替え不要。基本的には目地の補修だけで30年以上維持可能です。
ただし、施工の精度が低いとタイルの浮きや剥離が起きることがあります。重さもあるため、下地補強や施工管理が重要です。また、初期費用は他素材より高め。
しかし、メンテナンス費まで含めると総コストは意外と安くなるケースもあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| メンテ不要で超高耐久 | 初期費用が高い |
| 高級感と資産価値が高い | 剥離トラブル時の補修コストが高い |
総評:一度の投資で長く美観を維持できる素材。施工品質と保証体制を重視すれば、50年スパンでの最強外壁です。
7 ALC(軽量気泡コンクリート)

ALC(Autoclaved Lightweight Concrete)外壁は、内部に気泡を含む軽量コンクリートで作られた高性能素材です。断熱・遮音・防火性能に優れ、寒冷地や二世帯住宅などにも最適です。
欠点は、吸水性が高くコーキング管理が重要な点。目地から水が入ると内部に湿気がこもり、凍害や劣化につながる可能性があります。
したがって、塗膜の防水性を維持する再塗装が不可欠です。塗り替えの際は、弾性塗料や高耐候シリコン系塗料の使用がおすすめです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 高断熱・防火・遮音に優れる | 吸水しやすく塗膜管理が必要 |
| 軽量で建物への負担が少ない | コーキング劣化で防水性が低下 |
総評:性能面では最上位クラス。塗装メンテを怠らなければ、半世紀以上快適に保てる外壁材です。
簡単30秒でお見積♪
環境・立地別で考える“最適な外壁選びの指針”

外壁材は「性能が良いものを選べば安心」と思われがちですが、実際は“地域との相性”が最も重要です。
海沿いでは塩害、山間部では凍害、都市部では排気ガスや火災リスクなど、立地によって外壁のダメージ要因はまったく異なります。
ここでは、海辺・雪国・湿潤地域・都市部という4つの代表環境ごとに、最適な外壁選びの考え方をわかりやすく解説します。
多雪・豪雨地域での耐候性・水切り配慮
雪が多い地域や雨量の多い地域では、水の滞留と凍結膨張による劣化が問題になります。
外壁の表面に水が残ると、冬季には凍って膨張し、ひび割れや塗膜剥離を起こします。これを防ぐには「排水・通気設計」と「防水層の維持」が重要です。
| 重視すべきポイント | 理由 |
|---|---|
| 通気構法(胴縁+防水シート) | 外壁裏に湿気をためず凍害を防ぐ |
| 水切り金具の設置 | 雨水の逃げ道を確保 |
| 高弾性塗料の採用 | 雪の重みや凍結によるクラックを吸収 |
素材としては、ALCや金属系サイディングが相性良好。ALCは断熱性が高く、結露や凍害を防止します。金属系は軽量なため、積雪時の構造負担が小さいのも利点です。
塗り処ハケと手の現場では、屋根からの雪滑りによる衝撃対策も考慮し、1階部分に樹脂系や弾性塗装を組み合わせるケースもあります。
また、外壁下部の泥はねやカビ対策として、撥水塗料やフッ素コートの使用を推奨。
総評:雪・雨対策は「水をためない設計」+「柔軟な塗膜」+「耐凍結素材」の3点で決まります。
高温多湿な地域でのカビ・結露対策を意識した外壁
梅雨や夏の湿気が多い地域では、外壁の通気と防カビ性能が重要です。特に北面の壁や日陰部分は、カビや藻の繁殖が発生しやすく、見た目の劣化だけでなく素材の腐食にもつながります。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 通気層の確保 | 外壁裏に空気が流れる構造で湿気を逃がす |
| 防藻・防カビ塗料の採用 | バイオ技術を活用した塗料が有効(例:日本ペイント「パーフェクトトップ」など) |
| 下地断熱の適正化 | 壁内結露を防ぎ、カビ発生を根本から抑制 |
塗り処ハケと手では、千葉県の沿岸・湿地帯エリアで「低汚染性塗料+光触媒塗料」を採用。
光触媒が太陽光で汚れを分解し、雨で自然洗浄される仕組みを利用しています。これにより、10年以上カビが発生しないケースも確認されています。
また、外壁下部の換気口周辺にカビが集中する場合は、室内の湿度バランスも調整が必要。エアコンや除湿機だけでなく、外壁通気層の改善で根本から解決できます。
総評:湿気対策の外壁は「通気・防カビ・断熱」の三位一体。塗膜だけでなく、壁の“呼吸”を意識することが大切です。
防藻・防カビには塗り処ハケと手が使用している光触媒がおすすめです♪
都市部・防火地域での法規適合性と選べる素材
都市部では、隣家との距離が近く火災リスクが高いため、防火性能の高い外壁を選ぶ必要があります。建築基準法では「防火地域・準防火地域」に指定されているエリアでは、国土交通省の認定材料(NM-○○)を使用することが義務です。
| 適合素材 | 特徴 |
|---|---|
| 窯業系サイディング(防火認定品) | 多くのメーカーが耐火性能を取得済み |
| ALCパネル | 無機質素材で燃えにくく、遮音・断熱にも優れる |
| タイル外壁 | 不燃材の代表格で、メンテナンスも少ない |
また、都市部では排気ガスや粉塵による「外壁汚れ」も問題です。塗り処ハケと手では、セルフクリーニング機能付き塗料(光触媒・超低汚染型)を併用し、長期的な美観維持を実現しています。
防火地域では、開口部(窓・ドア)まわりのシーリング材も耐熱・不燃タイプを使用することが推奨されます。
簡単30秒でお見積♪
外壁材選定後に考える“長期維持と塗装/修繕戦略”
外壁をどの素材で仕上げても、メンテナンスを怠れば寿命は一気に短くなります。外壁の耐久年数は「素材」よりも「塗装と補修の管理」で決まるのが実際の現場です。
塗り処ハケと手では、施工直後よりも“その後10年をどう守るか”を重視しています。
ここでは、外壁材ごとのメンテ周期や劣化サイン、塗料の選び方、再塗装の費用感、重ね張り判断の目安など、長持ちのための現実的な戦略を具体的にお伝えします。
外壁材ごとの典型メンテ周期と劣化サイン
外壁は「まだきれいだから大丈夫」と放置されがちですが、見た目よりも内部の劣化が先に進んでいることが多いです。
以下は外壁材別のメンテ周期と代表的な劣化サインをまとめた一覧です。
| 外壁材 | メンテ周期の目安 | 主な劣化サイン |
|---|---|---|
| 窯業系サイディング | 10〜12年 | シーリングのひび割れ・反り・色あせ |
| 金属系サイディング | 15〜20年 | 退色・サビ・熱膨張による波打ち |
| 樹脂系サイディング | 20〜30年 | 退色・軽微なチョーキング |
| 木質系サイディング | 3〜5年 | 変色・カビ・反り・塗膜剥がれ |
| モルタル | 8〜10年 | ひび割れ・苔・塗膜浮き |
| タイル | 20年以上 | 目地の割れ・タイルの浮きや剥離 |
| ALC | 10〜15年 | コーキングの割れ・白華現象(白い粉) |
たとえば、窯業系サイディングではコーキング劣化から雨水が侵入し、下地が膨張して反るケースが非常に多いです。モルタルでは細かいひび割れから水が入り込み、内部鉄筋を腐食させることもあります。
塗り処ハケと手では、「塗り替え=再生のタイミング」と考え、外壁材に応じた専用塗料と下地処理を組み合わせています。
劣化は外観の変化ではなく、“触ったときの粉・反り・目地割れ”がサインと覚えておくと安心です。
塗料選び(耐候性・遮熱性・防水性)と相性チェック
外壁材と塗料の相性を誤ると、せっかくの塗り替えが数年で劣化することもあります。
塗り処ハケと手では、下地の素材・環境・希望耐用年数に合わせて塗料を厳選。特に以下の3性能を重視します。
| 性能 | 説明 | 向いている環境 |
|---|---|---|
| 耐候性 | 紫外線・雨風への耐久性。高耐候シリコン・フッ素・無機塗料が代表。 | 全地域共通 |
| 遮熱性 | 太陽熱を反射し、外壁温度上昇を抑える。室温2〜5℃低下効果も。 | 日射が強い地域 |
| 防水性 | 雨水の浸透を防ぎ、カビ・腐食を防止。弾性塗料やラジカル塗料が有効。 | 雨・湿気が多い地域 |
たとえば、金属サイディングに一般塗料を塗ると熱膨張で塗膜が割れる場合があります。逆にモルタルには伸縮性の高い弾性塗料が最適です。
また、最近人気のラジカル制御塗料は、チョーキング(白化)を抑えつつコストパフォーマンスも高いため、窯業系の再塗装に最適。
補修・再塗装コストの中長期見通し

外壁の塗装コストは「今いくらかかるか」ではなく、「30年間でいくら使うか」で考えるのが正解です。
短期で安い塗料を選ぶより、長持ちする塗料を選ぶ方が結果的に総コストが下がるケースが多いです。
| 塗料種類 | 耐用年数 | 1回あたりの相場(30坪) | 30年の想定総額 |
|---|---|---|---|
| ウレタン | 7〜10年 | 約80〜110万円 | 約210万円 |
| シリコン | 10〜13年 | 約100〜140万円 | 約180万円 |
| フッ素 | 15〜20年 | 約130〜160万円 | 約140万円 |
| 無機塗料 | 20〜25年 | 約140〜180万円 | 約160万円 |
つまり、「初期費用が高い=損」ではなく、「再塗装回数を減らす=得」なのです。
塗り処ハケと手の施工実績でも、無機塗料を選んだお客様の再塗装周期は平均18年超。長期で見れば約40万円以上の節約になります。
また、外壁材ごとに補修範囲を最小化する“部分塗装・部分張替え”を組み合わせることで、コスト効率をさらに上げることが可能です。
総評:外壁は「一度の出費」より「一生の維持費」で考えることが、後悔のない選択につながります。
外壁材の“重ね張り・張替え”判断基準
外壁のリフォームには、「塗り替え」「重ね張り」「張替え」という3つの選択肢があります。
塗り処ハケと手では、外壁診断を行い“寿命の見極め”を重視しています。
以下は判断の目安です。
| 状況 | 推奨施工 | 理由 |
|---|---|---|
| 表面の色あせ・チョーキング | 塗り替え | 下地が生きている |
| シーリング劣化・一部反り | 重ね張り | 下地保護しつつ外観改善 |
| 広範囲の膨れ・腐食・水侵入 | 張替え | 構造体の劣化が進行 |
重ね張りは既存壁を残して新しいサイディングを張る方法で、廃材が少なく工期も短いのがメリット。
一方、内部が腐食している場合に重ね張りをすると、見た目だけ直って中がボロボロという事例もあります。
そのため、施工前に必ず外壁赤外線診断・含水率測定を行うのが理想です。
塗装会社選びのチェックポイント
外壁を長持ちさせる最大の秘訣は、“良い職人に出会うこと”です。
どんな高級塗料も、施工精度が低ければ5年で劣化します。塗り処ハケと手が考える「良い塗装会社の条件」は以下の通りです。
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 診断力 | 現地調査で外壁・屋根を赤外線や高所カメラで診断しているか |
| 見積書の透明性 | 塗料名・メーカー・塗布量(㎡単価)が明記されているか |
| 施工管理体制 | 一級塗装技能士・有資格者が現場管理を行っているか |
| 保証内容 | メーカー保証+自社保証のW保証かどうか |
| 口コミ・施工事例 | 写真付きの事例や実名口コミがあるか |
外壁塗装は“見積価格”ではなく、“安心して任せられるか”で選ぶのが本質です。
総評:塗料よりも人を選ぶ。信頼できる施工店との長い付き合いこそ、家を長持ちさせる最大の資産です。
簡単30秒でお見積♪
まとめ
この記事では、「外壁の種類と選び方」を軸に、環境・費用・耐久性をトータルで考える方法を解説しました。
外壁は「今きれいに見えるか」ではなく、「何年後も安心して住めるか」で判断するのが本当の成功です。
塗り処ハケと手では、見た目だけでなく“家の未来を守るための外壁提案”を行っています。
🔑この記事のポイント
-
外壁は「用途・地域性・維持コスト」で選ぶのが基本
-
主要7種類(窯業系・金属系・樹脂系・木質系・モルタル・タイル・ALC)にはそれぞれ強みと弱点がある
-
立地条件(海沿い・多雪・多湿・都市部)で最適素材は変わる
-
外壁寿命は素材より“メンテナンス管理”が決め手
-
塗料は「耐候性・遮熱性・防水性」のバランスで選ぶ
-
費用比較は“30年単位”で見ると、無機・フッ素塗料が最もお得
-
外壁リフォームは外観ではなく“内部診断”で判断
-
最後は「信頼できる職人・施工店を選ぶ」ことが長持ちの鍵
職人集団の塗り処「ハケと手」とは?
塗り処ハケと手とは、営業マンを一切置かず、職人だけで運営する塗装の専門集団です。
私たちの強みは以下の通りです!
- 完全自社施工・自社管理:職人が直接施工するため、中間マージンがなく、質の高い仕上がりをお手頃価格でご提供します。
- プロのカラーデザイナーによる無料シミュレーション:契約前に20種類以上のデザインを確認でき、理想の外観を具体的にイメージできます。
- 業界唯一の長期保証:木部・鉄部・樹脂など、競合では難しい部分も一応しっかり保証。
- 見積り後のしつこい営業は一切なし:お気軽にご相談・見積り依頼が可能です。
- 全国80拠点の地域密着サービス:迅速で適切な対応を心がけ、地域の特性を踏まえた最適なプランを提案します。
- 万全のアフターケア:施工後も安心のフォロー体制で、長くお付き合いさせていただきます。
職人の技術とデザイン力で、全国のお家を幸せ色に塗り替えています♪お気軽にお問い合わせください!