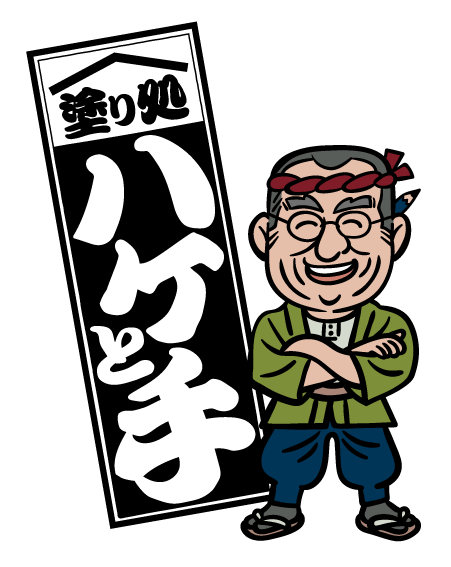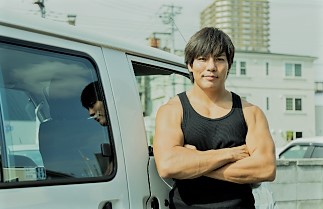2025.10.17
【初心者向け】モルタル壁の外壁塗装で失敗しないための完全ガイド
「モルタル壁の外壁塗装って本当にできるの?」──そう感じて検索された方へ。
モルタル壁は、風合いが魅力的な一方で、ひび割れ・白華・浮きなどの劣化が起こりやすい素材です。
実は、「どんな状態でも塗装できる」わけではありません。
正しい診断・補修・塗料選びを行わないと、せっかく塗り替えても数年で剥がれてしまうことも。
この記事では、モルタル壁の塗装可否の判断基準から、費用・工期・補修手順・塗料選び・信頼できる業者の見極め方まで、専門的な内容を分かりやすく解説します。
読むだけで、モルタル壁の塗装を「失敗しないための正しい流れ」がわかります。
✅この記事を読むと分かること:
-
モルタル壁は本当に外壁塗装できるのかが分かる
-
塗装できる壁・できない壁の見分け方が分かる
-
費用相場と追加費用の仕組みが分かる
-
下地補修と塗装の正しい手順が分かる
-
モルタル壁に合う塗料と艶の選び方が分かる
-
信頼できる業者と見積書の見分け方が分かる
簡単30秒でお見積♪
目次
モルタル壁は外壁塗装できる?結論:状態次第で「できる」が正解

結論から言えば、モルタル壁は外壁塗装が可能です。
ただし「すべてのモルタル壁が塗れるわけではない」という点が最大の注意点です。ひび割れや白華(はっか)・浮きなどの劣化が進んだ壁は、塗装してもすぐに剥がれたり膨れたりするリスクがあります。
塗装の可否は、下地の健全性と含水率、既存塗膜の状態によって判断されます。ここでは、「塗れる壁」と「塗れない壁」の違いを明確にし、プロが実際にどのように診断しているのかを具体的に解説します。
塗装ができるモルタル壁・できないモルタル壁の見分け方
モルタル壁の塗装可否は、外観だけでは判断できません。ポイントは下地が生きているかどうかです。
以下の表を参考にしてみましょう。
| 判定項目 | 塗装できる状態 | 塗装できない状態 |
|---|---|---|
| ひび割れ | 0.3mm以下のヘアークラック | 構造クラック(0.3mm以上) |
| 浮き | 局所的 | 全面にわたる浮きや剥離 |
| 白華(はっか) | 一部表面に軽度 | 広範囲で粉状・結晶状の析出 |
| 含水率 | 10%未満 | 15%以上(水分が抜けきっていない) |
| 下地 | 叩くと「コンコン」音 | 「ボコボコ」「鈍い音」=中が浮いている |
特に含水率は重要で、日本建築学会の基準でも10%以上は再塗装に不適とされています。
見た目がきれいでも、水分が残ったまま塗装すると内部膨れを起こし、最悪の場合は数か月で剥離するケースも。
判断に迷ったら、業者に含水率測定器で数値を見せてもらうことが確実です。
ひび割れ・白華・浮きなど“塗装NG”サインをチェック
モルタル壁の劣化サインを放置すると、見た目以上に内部が痛んでいます。特に以下の3つは“塗装前の危険信号”です。
-
ひび割れ(クラック)
0.3mmを超えると、塗料ではカバーできません。内部に雨水が入り、鉄筋が錆びて爆裂(内部膨張)を起こすおそれがあります。
⇒対策:Vカット・Uカット補修+樹脂モルタルで再成形。 -
白華(はっか)現象
壁表面に白い粉や結晶が浮く症状で、水分の通り道がある証拠です。塗装しても再発します。
⇒対策:原因箇所(ひび・雨仕舞不良)を特定し、乾燥後に下地調整。 -
浮き・剥離
叩くと「ボコボコ」と鈍い音がする部分は、内部が浮いています。塗装しても密着しません。
⇒対策:浮き部分を除去後、左官補修で再密着。
このような症状がある場合は、まず補修→乾燥→塗装の順で工程を組むことが大切です。塗装だけを急ぐと、数年で同じ症状が再発します。
モルタル壁の塗装を成功させるための診断ポイント5選
塗装の成否は「塗る前の診断」にあります。以下の5項目を押さえれば、失敗リスクをほぼゼロにできます。
| 診断ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 含水率 | 10%以下であること(高いと膨れや剥離リスク) |
| ② クラック幅 | 0.3mm以下なら弾性塗料で追従可能 |
| ③ 白華の有無 | 白華が残っている場合は中性化が進行中 |
| ④ 既存塗膜の密着力 | テープテストで剥がれなければOK |
| ⑤ 下地の強度 | 指で触って粉が出ないか(チョーキング確認) |
これらをプロは専用機器や目視で行いますが、DIYでも含水率計・ルーペ・マスキングテープがあれば概ね確認可能です。
特に「白華+チョーキング」が同時に出ている壁は再塗装の限界サインなので、下地補修を優先しましょう。
プロが行う可否判断とDIYでの簡易チェック方法
プロの現場調査では、塗装の可否を科学的根拠に基づいて判断します。代表的な手法は次のとおりです。
| チェック項目 | プロの診断方法 | DIYでの簡易確認 |
|---|---|---|
| 含水率 | 含水率計で測定(10%以下が理想) | 晴天時でも湿り気が残るならNG |
| クラック幅 | ルーペ+クラックスケールで測定 | 爪が入るほどのひびは要補修 |
| 塗膜密着 | クロスカット+テープ試験 | テープで剥がれるなら塗り替え前処理必須 |
| 下地強度 | 打診棒で音の違いを確認 | 金属スプーンで軽く叩いても判断可 |
DIYでも可能ですが、「含水率」「構造クラック」だけは専門機器が必要なため、無料診断を依頼するのがおすすめです。
塗装は“塗る作業”よりも、“塗れるかどうかの判断”の方が難しい作業です。判断を誤ると、仕上がりよりも先にトラブルが出るケースが多いため、プロの視点で状態を見極めることが成功の鍵です。
簡単30秒でお見積♪
モルタル壁の外壁塗装費用と工期:相場よりも“補修量”で差がつく

モルタル壁の外壁塗装費用は、「建物の大きさ」よりも劣化の進行度や補修量で大きく変わります。
同じ30坪でも、ひび割れや白華、下地の浮きが多い住宅は、費用が20〜40万円前後高くなるケースも珍しくありません。
つまり、見た目以上に「壁の内部状態」でコストが決まります。
この記事では、モルタル壁の塗装費用の内訳・追加費用の発生理由・工期の目安・見積書で損をしないチェック項目まで、初めての方でも理解できるように具体的に解説します。
一般的な費用相場(30坪・150㎡)と内訳をリアルに解説
モルタル壁の外壁塗装は、延床30坪(外壁約150㎡)で110万〜200万円前後が一般的な相場です。
ただし、単価の内訳を理解しないまま金額だけを比較するのは危険です。
費用構成の基本は以下の通りです。
| 項目 | 費用目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 足場・養生 | 15〜20万円 | 作業安全と塗料飛散防止 |
| 高圧洗浄 | 3〜5万円 | コケ・汚れ除去、密着向上 |
| 下地補修 | 5〜20万円 | クラック・白華・浮き対応 |
| 下塗り | 10〜30万円 | 吸い込み防止・密着強化 |
| 中・上塗り | 30〜70万円 | 耐候性・意匠仕上げ |
| 諸経費 | 10〜30万円 | 運搬費・管理費など |
塗料の種類でも費用は変動します。
一般的にシリコン塗料が最も採用率が高く、フッ素系や無機塗料は耐用年数が長い分、+15〜30%の費用増が目安です。
モルタル壁は下地処理の工程が多いため、「安すぎる見積もり」は下地工程の省略が疑われます。
価格だけでなく、何にいくらかかっているかを把握することが失敗防止の第一歩です。
クラック補修や下地調整で追加費用が発生する理由
モルタル壁は、乾燥や地震・振動によって細かなひび(クラック)が発生しやすい素材です。
そのため、塗装前には下地補修を行うのが基本ですが、この補修量が追加費用の発生要因になります。
主な補修内容と単価の目安をまとめると以下の通りです。
| 作業内容 | 単価目安 | 補足 |
|---|---|---|
| ヘアークラック補修 | 300〜500円/m | 弾性フィラー充填で追従性確保 |
| 構造クラック補修 | 1,000〜1,500円/m | Vカット+樹脂モルタル補修 |
| 浮き補修 | 2,000〜3,000円/箇所 | 斫り+再左官処理 |
| 白華除去 | 1,000〜2,000円/㎡ | 酸洗い・乾燥養生が必要 |
クラック補修を怠ると、数年後に再び剥がれや膨れが起きる可能性が高まります。
業者によっては「軽微な補修をサービス」とするところもありますが、構造クラックや浮きは別途費用が発生するのが一般的です。
つまり、見積金額の差は「下地処理の深さ」の差とも言えます。
“安く見せる”より“長く持たせる”見積もりを選ぶのが結果的に経済的です。
工期の目安と天候・季節が品質に与える影響
モルタル壁の外壁塗装は、一般的な住宅で10〜14日前後の工期がかかります。
その内訳を工程ごとに見ると以下の通りです。
-
足場組立・養生 … 1日
-
高圧洗浄 … 1日
-
下地補修・乾燥 … 2〜3日
-
下塗り … 1日
-
中・上塗り … 2〜3日
-
点検・片付け … 1日
ただし、天候が悪化すると乾燥時間を確保するために1〜3日程度の延長が発生することもあります。
特に湿度が高い梅雨時期や、気温5℃以下の冬季は塗料が硬化しづらく、品質が著しく低下するリスクがあります。
JISおよび主要塗料メーカーの基準では、「湿度85%以上または気温5℃未満では施工禁止」と定められています。
このため、優良業者ほど「天候による延期」を柔軟に行います。
工期を無理に短縮するよりも、十分な乾燥時間を確保する方が塗膜寿命が倍以上伸びると覚えておきましょう。
塗り処ハケと手の施工の流れはコチラから確認できます♪
見積書で“損しない人”が必ず確認している項目とは
外壁塗装の見積書を見るとき、多くの人が「合計金額」だけで判断しがちです。
しかし、損をしない人は見積書の“中身”を細かく確認しています。
特に次の5つは必ずチェックすべきポイントです。
| チェック項目 | 注目ポイント |
|---|---|
| ① 塗装面積 | 現地採寸または図面からの正確な㎡数が記載されているか |
| ② 下地補修 | クラックm数や補修範囲が具体的に書かれているか |
| ③ 塗料名・メーカー | 製品名・ロット・耐用年数が明記されているか |
| ④ 下塗り仕様 | シーラー・フィラーの区別があるか |
| ⑤ 保証条件 | 保証年数・範囲・書面発行の有無 |
また、「外壁塗装工事 一式」としか書かれていない見積書は避けましょう。
これでは内容を比較できず、トラブルの原因になります。
信頼できる業者は、1㎡単価や補修単価を明示した詳細見積書を提示します。
数字の裏側に「どんな作業が含まれているか」を理解することが、最終的な満足度を左右します。
モルタル壁の下地補修と外壁塗装の手順:長持ちの秘訣は“下地づくり”

モルタル壁の外壁塗装を長持ちさせる最大のポイントは、下地補修をどれだけ丁寧に行うかにあります。
ひび割れや浮きを見逃したまま塗装しても、どんな高級塗料を使っても数年で剥がれや膨れが再発します。
特にモルタルは「呼吸する素材」であり、湿気・温度変化に敏感なため、塗る前の下地づくりが品質の8割を占めるといっても過言ではありません。
ここでは、クラック(ひび)の種類や補修方法、下地強化剤の選び方、そして補修を怠るリスクまで、専門家の視点で分かりやすく解説します。
ヘアークラックと構造クラックの違いと補修方法
モルタル壁に発生する「ひび割れ」は、すべて同じに見えても原因も対処法もまったく異なります。
基本的に、クラックは下記の2種類に分類されます。
| 種類 | 幅の目安 | 原因 | 対応方法 |
|---|---|---|---|
| ヘアークラック | 0.3mm以下 | 乾燥収縮・温度変化 | 弾性塗料または微弾性フィラーで追従 |
| 構造クラック | 0.3mm以上 | 地震・基礎沈下・構造歪み | Vカット/Uカット+樹脂モルタル補修 |
ヘアークラックは放置してもすぐに問題が出るわけではありませんが、水の侵入口になるため、塗装前にフィラー(厚みのある下地材)で埋める必要があります。
一方、構造クラックは建物の動きが原因のため、単なる塗料補修では再発します。
この場合はクラックをカットして内部を樹脂で充填し、再度モルタルを成形してから塗装するのが正解です。
国土交通省の建築仕上げ改修指針でも「構造クラックは単純な塗り替え不可」と明記されており、正しい補修工程こそが耐用年数を決める分かれ道になります。
ヘアクラックに関する詳細記事はコチラから!
構造クラックに関する詳細記事はコチラから!
浮き・剥離・中性化を見抜くチェックポイント
モルタル壁のもう一つの劣化トラブルが「浮き」や「剥離」、そして「中性化」です。
これらは表面では気づきにくいため、叩いたときの音や壁の色味の変化で判断します。
| チェック項目 | 症状 | 対策 |
|---|---|---|
| 浮き | 叩くと「ボコボコ」と鈍い音がする | 該当箇所を削り、左官で再接着 |
| 剥離 | 塗膜がめくれ・膨れ・粉化 | 不良塗膜を除去し、シーラー再塗布 |
| 中性化 | 表面が白っぽく、鉄筋近くが脆い | pH試験紙で確認、再アルカリ化処理 |
モルタルはセメント系素材のため、経年で酸性雨により中性化が進みます。
中性化すると鉄筋が錆び、内部から爆裂(膨張破壊)が起こる危険があります。
特に築20年以上の家では、塗装前に中性化試験(pH検査)を行うことが望ましいです。
この工程を省くと、どんな高耐久塗料でも数年で下地から劣化します。
つまり、下地の「健全性を診る」ことこそ最初の補修なのです。
下地を固めるシーラー・フィラーの正しい選び方
塗装の耐久性を決めるのは「上塗り塗料の種類」ではなく、下地と上塗りをつなぐ“接着剤”=下塗り材の選定です。
モルタル壁の場合、主に「シーラー」と「フィラー」の2種類が使われますが、それぞれ役割が異なります。
| 種類 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| シーラー | 吸い込みの多い下地 | 下地を固め、塗料の密着を高める |
| フィラー | ひび・凹凸が多い下地 | 厚みをつけて表面をなだらかに整える |
・シーラーは、経年で粉を吹いた(チョーキングした)モルタル面に有効。浸透して脆弱層を固める役割があります。
・フィラーは、微細なクラックや凹凸を埋める厚塗りタイプ。弾性のある素材を選ぶと再ひび割れを防げます。
特におすすめなのが微弾性フィラー+透湿性上塗りの組み合わせ。
湿気を逃がしつつ、雨水は通さない理想的な構造で、膨れ防止にも効果的です。
塗料メーカーの試験データでも、下塗りを正しく施工した場合と省略した場合では密着強度が約2倍になると報告されています。
補修を怠ると塗装が失敗する理由と再発リスク
「塗ればきれいになる」と考えるのは危険です。
モルタル壁は呼吸する素材であり、下地の痛みを無視した塗装は必ず再発します。
補修を怠った場合に起こる代表的なトラブルをまとめると次の通りです。
| 不具合 | 発生時期 | 原因 |
|---|---|---|
| 塗膜の膨れ | 1〜2年以内 | 含水率が高いまま塗装した |
| クラック再発 | 2〜3年 | 構造クラックを補修せず塗装 |
| 剥離・チョーキング | 3〜5年 | 下塗り不足・シーラー不適合 |
| 白華再発 | 通年 | 内部に水分経路が残っている |
実際、塗り替え後わずか数年でトラブルが発生する家の多くは、「下地補修を省略した見積もり」で施工されています。
特に格安業者が避ける傾向にあるのが「Vカット補修」や「浮き除去」。
一見仕上がりはきれいでも、内部では再び水分が回り、塗膜が押し上げられていくのです。
外壁塗装を“仕上げ工事”ではなく“下地再生工事”と考えることが、失敗を防ぐ最大のコツ。
表面の塗料よりも、目に見えない部分への手間こそが家を10年以上守ると覚えておきましょう。
簡単30秒でお見積♪
モルタル壁に最適な外壁塗装の塗料選び:風合いと耐久性を両立するコツ

モルタル壁の魅力は、手仕事ならではの質感と重厚感。
しかし、その風合いを守りながら長く持たせる塗料選びは、他の外壁材よりも難易度が高いといえます。
間違った塗料を選ぶと、ひび割れや膨れが再発したり、モルタル特有のマットな質感が失われることも。
ここでは、弾性・透湿などの塗料タイプの違い、リシン・スタッコ仕上げを活かす塗り方、艶の選び方、そして機能性塗料の費用対効果まで、「見た目」と「性能」を両立する選定基準を詳しく解説します。
弾性・微弾性・透湿型の違いと選び方の基準
モルタル壁はひび割れやすいため、塗料の「伸びる力(弾性)」が欠かせません。
一方で、湿気を閉じ込めると膨れの原因にもなるため、塗料選びは「弾性+透湿性」のバランスが重要です。
まずは3タイプの違いを整理しましょう。
| 種類 | 特徴 | 向いている壁 |
|---|---|---|
| 弾性塗料 | 伸縮性が高く、ひびに追従 | クラックの多い壁 |
| 微弾性塗料 | 弾性と通気性の中間タイプ | 一般的なモルタル壁 |
| 透湿型塗料 | 湿気を逃がし、膨れを防ぐ | 湿度が高い地域・北面壁 |
日本建築学会の報告によると、モルタル壁の膨れトラブルの約7割は通気性不足が原因とされています。
そのため、築年数が経った住宅や日当たりが悪い立地では、微弾性+透湿性の塗料が最も安定します。
逆に、弾性塗料を厚く塗りすぎると内部結露が発生しやすく、長期的に剥離リスクが高まるため注意が必要です。
迷ったら「弾性下塗り+透湿上塗り」の組み合わせが、風合いと耐久性の両立に最適です。
リシンやスタッコ仕上げを損なわない塗装方法
モルタル壁の美しさは、リシンやスタッコのような凹凸模様の陰影にあります。
しかし、一般的な塗装方法で厚く塗ってしまうと、この繊細な風合いが消えてしまいます。
つまり、「守るための塗装」が「個性を壊す塗装」になってしまうのです。
この仕上げを残すコツは以下の3点です。
-
高圧洗浄は低圧設定で行う
表面の骨材(砂粒)を飛ばさないため。 -
下塗りは浸透型シーラーを使用
表面を固めるだけでなく、凹凸を潰さない。 -
中・上塗りは薄塗りローラー or 吹付け工法
骨材を残しながら均一に塗膜を形成。
また、「リシン仕上げ」は透湿性が高いため、密閉型の弾性塗料を使うと内部に水分がこもりやすくなります。
スタッコ仕上げも同様で、厚塗りタイプの弾性塗料は避けるのが原則。
意匠を保ちたい場合は、メーカー推奨の「リシン・スタッコ専用塗料(例:水性アクリルシリコン透湿型)」を選ぶと、凹凸を残しつつ新築のような質感を再現できます。
艶のあり・なしで変わる見た目とメンテナンス性
塗料には「艶あり」「3分艶」「艶消し」などの種類があります。
見た目だけの違いと思われがちですが、実は汚れの付きやすさ・耐久性にも影響します。
| 艶レベル | 見た目の印象 | 汚れにくさ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 艶あり | 光沢が強く、清潔感のある印象 | ◎ | 雨筋汚れが流れやすい |
| 3分艶 | 自然なツヤで落ち着いた雰囲気 | ○ | 住宅街に多い人気タイプ |
| 艶消し | マットで重厚、モルタルらしい質感 | △ | 汚れが付くと目立ちやすい |
モルタル壁本来の風合いを残したい場合、3分艶〜艶消しがおすすめです。
ただし、艶消しは表面の凹凸に汚れが溜まりやすいため、定期的な洗浄が必要になります。
「見た目を取るか、メンテナンス性を取るか」で迷った場合、半艶(3分〜5分艶)仕上げが最もバランスが良く、どの環境でも失敗しにくい選択肢です。
塗装は“質感デザイン”でもあるため、見積もりの際は実際の艶見本板を外壁に当てて確認してから決めるのが確実です。
遮熱・防藻・防カビなど機能性塗料の費用対効果
最近では、耐久性に加えて「機能性」で塗料を選ぶ方も増えています。
特に注目されているのが、遮熱・防藻・防カビ・セルフクリーニングなどの高機能系塗料です。
それぞれの特徴と費用目安をまとめると以下の通りです。
| 機能 | 効果 | 費用上乗せ目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遮熱 | 室温を最大3〜5℃下げる | +10〜15% | 屋根・南面に効果的(JAXAデータ) |
| 防藻・防カビ | 湿気や北面の藻・カビ抑制 | +5〜10% | 日当たりの悪い立地に有効 |
| セルフクリーニング | 雨で汚れを流す親水機能 | +10〜20% | 白・淡色塗装におすすめ |
これらは一見コストアップに見えますが、長期的には再塗装サイクルを延ばす効果があります。
特に、湿度の高い地域や樹木が近い環境では、防藻・防カビ性能があるだけで外観維持年数が2〜3年伸びることも。
ただし、機能性塗料は下地との相性が重要で、透湿性を妨げるタイプを選ぶと逆効果になる場合があります。
そのため、塗装前には「通気性を確保した上で機能を足す」という視点で選ぶことが、費用対効果を最大化するポイントです。
モルタル壁の外壁塗装で失敗しない業者選びと進め方

モルタル壁の外壁塗装は、塗料よりも業者選びのほうが難しいといわれます。
なぜなら、仕上がりや耐久年数は「誰が塗るか」で決まるからです。
同じ塗料を使っても、下地補修の丁寧さや乾燥時間の管理が違えば結果はまったく異なります。
この章では、現地調査で確認すべき7項目、良い見積書の見分け方、完了後のチェックリスト、そしてアフター保証で業者を見極めるコツを、現場目線で分かりやすく解説します。
現地調査でチェックすべき7項目(含水率・クラック・白華など)
信頼できる業者は、見積りの前に必ず「現地調査」を行います。
この調査をどれだけ丁寧に行うかで、塗装の品質が決まります。
以下は、プロが必ず確認する7つの基本項目です。
| 項目 | 内容 | 見る目的 |
|---|---|---|
| ① 含水率 | 壁の内部湿度を測定(10%以下が理想) | 膨れ・剥がれ防止 |
| ② クラック | 幅と深さを測定(0.3mm以上は構造クラック) | 補修方法の判断 |
| ③ 白華(はっか) | 白い粉・結晶が出ていないか | 水分経路の特定 |
| ④ 浮き・剥離 | 叩いて音を確認 | 下地の健全性チェック |
| ⑤ 旧塗膜の状態 | 剥がれ・チョーキングの有無 | 密着性の判断 |
| ⑥ 周囲環境 | 日当たり・風通し・植栽 | カビ・苔発生リスク |
| ⑦ 雨仕舞 | 笠木・サッシ周りの防水確認 | 雨漏り対策 |
この7項目のうち、含水率測定を省略する業者は要注意。
JIS規格では「含水率10%以上は塗装不可」と明示されています。
見た目だけで判断する業者よりも、データを測定して説明してくれる業者が確実です。
また、調査結果を写真付きで報告してくれる会社は、施工中も透明性が高い傾向にあります。
信頼できる業者が提出する“良い見積書”の特徴
良い見積書は、単に金額が書かれた紙ではありません。
信頼できる業者ほど、「なぜこの費用になるのか」が分かる構成にしています。
以下の5点をチェックすれば、見積書の質が一目で分かります。
| チェック項目 | 理想的な内容 |
|---|---|
| ① 面積の根拠 | 図面・実測で算出された㎡数を明記 |
| ② 補修範囲 | クラックm数・補修箇所を具体的に記載 |
| ③ 使用塗料 | メーカー・品番・耐用年数・塗布回数を明示 |
| ④ 下塗りの種類 | シーラー or フィラーなど仕様が明確 |
| ⑤ 保証条件 | 年数・範囲・発行形態(書面 or 口約束)を明記 |
逆に、「外壁塗装工事一式」「補修含む」としか書かれていない見積書は要注意。
こうした“ざっくり見積り”は、後から追加請求されるケースもあります。
また、3回塗り(下塗り+中塗り+上塗り)を明記しているかも重要です。
たとえ価格が安くても、下塗りを省略していれば本来の耐久性は半減します。
信頼できる業者は、見積書の中で「工事の透明性」を示してくれるものです。
施工後トラブルを防ぐ完了チェックリスト
工事完了後は「きれいに見える」だけでは安心できません。
塗膜の密着不良や塗り残しは、見た目では気づきにくいからです。
施工後に失敗を防ぐためのチェックポイントを以下にまとめます。
| チェック項目 | 確認方法 |
|---|---|
| ① 塗膜の均一性 | 光の反射でムラやローラー跡がないか確認 |
| ② 塗り残し | サッシ枠・軒天・雨樋裏を目視点検 |
| ③ クラック再発 | 仕上げ後も新しいひびが出ていないか |
| ④ 養生の剥がし残し | サッシやガラスにテープ跡が残っていないか |
| ⑤ ゴミ・塗料飛散 | 敷地や車に塗料が付着していないか |
さらに、完了検査では業者立ち会いで一緒に確認するのが理想です。
この際、「塗膜厚計」で膜厚を測定してくれる業者は信頼できます。
膜厚が仕様値(一般的には100〜150μm)に達していなければ、耐久性に影響します。
施工完了後には、施工写真や保証書を受け取ることを忘れずに。
これらが揃っていれば、アフター対応の際にも確実な証拠になります。
保証・アフター対応で判断する業者選びのコツ
外壁塗装のトラブルで最も多いのが、施工後の対応の遅さです。
保証内容を事前に確認しておかないと、何かあっても「対象外」とされることがあります。
信頼できる業者は、施工前に書面で保証条件を提示します。
| 保証項目 | 理想的な内容 |
|---|---|
| 保証期間 | 5〜10年(塗料・施工ごとに異なる) |
| 保証範囲 | 剥がれ・膨れ・変色などの再施工対応 |
| 保証形態 | 書面発行+登録番号付き |
| 点検頻度 | 1年・3年・5年など定期点検あり |
特に大切なのは、「塗料メーカー保証+施工店保証のダブル体制」があるかどうか。
メーカー保証は塗料性能を、施工店保証は職人の施工品質を担保します。
また、地域密着型の業者ほど緊急対応が早く、保証履行率も高いという実例もあります。
国土交通省のリフォーム紛争事例でも、「保証書の未交付」がクレーム原因の約3割を占めています。
契約時に保証書が交付されない場合は、後々トラブルになる可能性が高いため、必ず書面で受け取りましょう。
簡単30秒でお見積♪
まとめ
本記事では、「モルタル壁の外壁塗装」をテーマに、塗装できる条件・費用・補修・塗料選定・業者選びまでを一気通貫で解説しました。
モルタル壁は“塗る”ことよりも、“塗れる状態を整える”ことが最も重要です。
そのためには、含水率・クラック・下地強度などの診断と、正しい下地補修・塗料選び・職人技術の3本柱が欠かせません。
🔑本記事の重要ポイント:
-
モルタル壁の塗装可否は「下地の状態」で決まる
-
含水率10%以下・構造クラックなしが理想条件
-
費用は建物の大きさより「補修量」で差が出る
-
下地補修と透湿性塗料の組み合わせが長持ちの秘訣
-
艶・仕上げ・機能性で風合いと耐久性を両立できる
-
信頼できる業者は診断・見積・保証が明確
モルタル壁の外壁塗装は、状態を見極め、正しい手順で行えば“新築同様の美しさ”が10年以上続きます。
「塗る前の準備こそが最高の仕上がりを生む」──これを覚えておくだけで、あなたの住まいの価値は大きく変わります。
職人集団の塗り処「ハケと手」とは?
塗り処ハケと手とは、営業マンを一切置かず、職人だけで運営する塗装の専門集団です。
私たちの強みは以下の通りです!
- 完全自社施工・自社管理:職人が直接施工するため、中間マージンがなく、質の高い仕上がりをお手頃価格でご提供します。
- プロのカラーデザイナーによる無料シミュレーション:契約前に20種類以上のデザインを確認でき、理想の外観を具体的にイメージできます。
- 業界唯一の長期保証:木部・鉄部・樹脂など、競合では難しい部分も一応しっかり保証。
- 見積り後のしつこい営業は一切なし:お気軽にご相談・見積り依頼が可能です。
- 全国80拠点の地域密着サービス:迅速で適切な対応を心がけ、地域の特性を踏まえた最適なプランを提案します。
- 万全のアフターケア:施工後も安心のフォロー体制で、長くお付き合いさせていただきます。
職人の技術とデザイン力で、全国のお家を幸せ色に塗り替えています♪お気軽にお問い合わせください!
全国90店舗以上! ハケと手は、お客様に寄り添った「サービス業」として塗装を行っております。 「信頼できる塗装店にお願いしたい」
外壁・屋根塗装なら「ハケと手」へ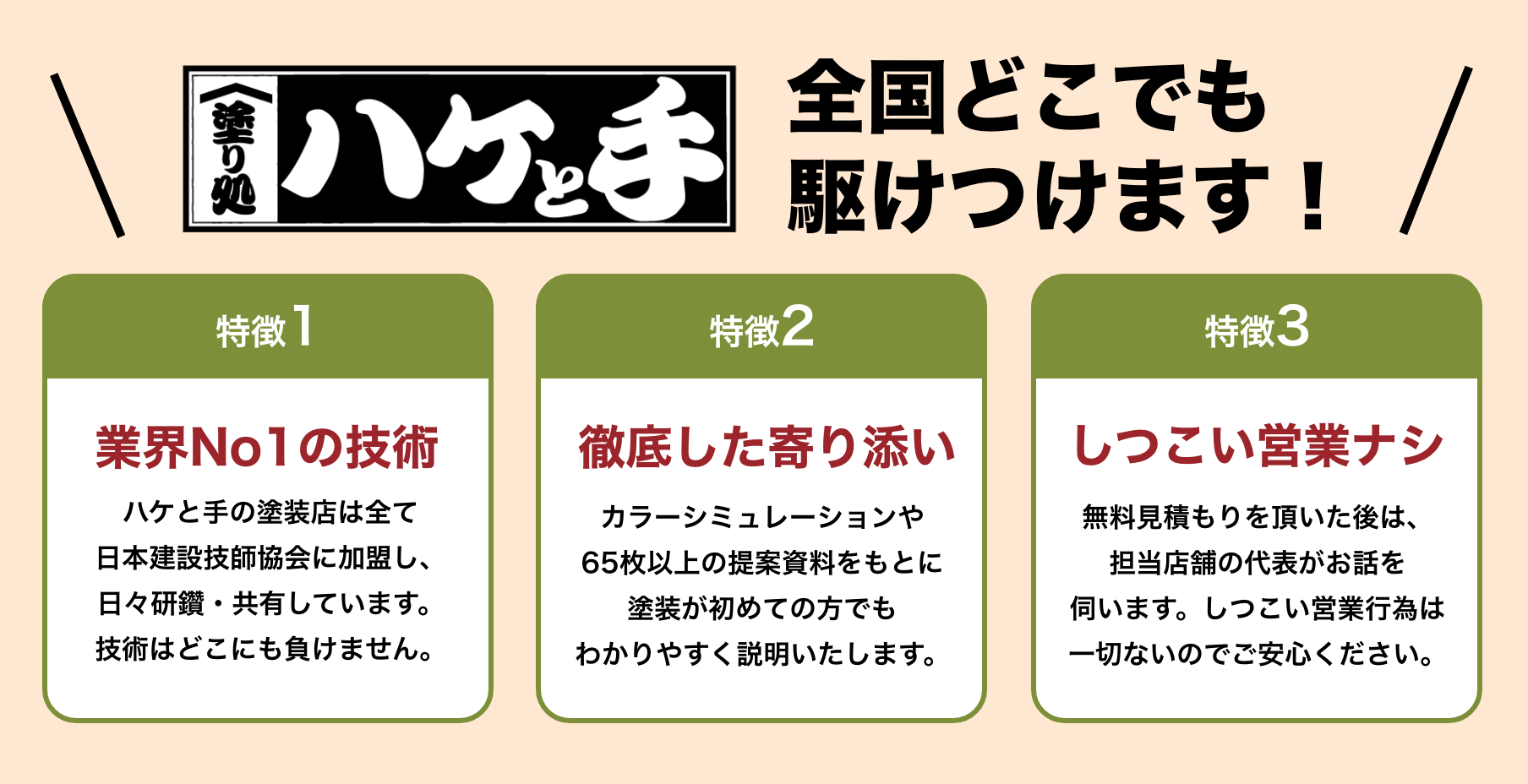
「しつこい営業されたくない…」
そんな方にこそおすすめなのが「塗り処ハケと手」
ためしに一度、無料見積もりをしてみてください♪